- 毎月、家計簿とにらっめこしているのにお金が貯まらない
- 節約料理もがんばっているのに食費が減らない
- 家族の協力もして欲しいのに何か無関心・・・家族にもっとお金の話を聞いてほしい
毎月なんでお金が残らないんだろう?むしろ赤字の状況が続いてしまっている。
家計簿はつけているのに、なんとなく不安。そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?
子育てに仕事に毎日バタバタで、お金のことはつい後回しになりがちではないでしょうか?
私も毎月赤字が続き、何とかしなければと気持ちばかり焦っていました。
しかし、支出の見える化を図ったことにより家計の中でムダ使いに気づき、将来の不安も少しずつ減っていきました。
今回は、FP2級資格保持者の私が実践している「支出の見える化のコツ」を紹介します。
この記事を読めば、家計管理って何をすれば良いのか?という課題解決に向けた手立てとなります。
忙しい方でもできる方法なので、ぜひ最後まで読んでください。
そもそも「見える化」とは?
皆さんの考える家計の見える化とはどんな状況だと思いますか?
考え方は個人差があると思いますが、以下の項目があげられます。
- 家計の流れがパッと把握できる状態であること
- 毎月いくら使っているのか、固定費・変動費が分かる状態であること
- 貯金ができない原因がわかること

上記の情報が目に見えると、「何となく不安」が「ちょっと安心」に変わります。
見える化のための3ステップ
- ステップ1:固定費と変動費をざっくり書き出す
- ステップ2:家計簿アプリ等で記録(またはExcel)
- ステップ3:「振り返る時間」を週1でも行う
見える化を行うために以下の3ステップをあげてみました。
注意事項としては、一度にまとめて行わないことです。もちろん、1〜2日間ほど休みが取得できる方は一気に行っても構いませんが、時間の確保が難しい方もいらっしゃると思います。やる気満々で実践しようと思ったら、想像以上に時間がかかってしまい、次のステップに進むのが困難になる可能性があります。焦らず、1つずつこなして行きましょう。
ステップ1:固定費と変動費をざっくり書き出す
まず、ステップ1としてざっくりでよいので、固定費と変動費を書き出してみましょう。
例えば以下のようなものがあげられます。
- 固定費:家賃・保険・通信費・サブスク費など
- 変動費:食費・日用品・教育費・医療費など
最初は紙でも構いません。とにかく一度書いてみることが第一歩となります。
1ヶ月分をざっくり把握するだけでも、「我が家はこんなに使っていたのか…」と気づきが生まれます。
ステップ2:家計簿アプリ等で記録(またはExcel)

ステップ2としては、家計簿アプリ等で日々の支出を記録していきます。
ポイントは以下の通りです。
- 忙しい人向け → 家計簿アプリ(例:マネーフォワードME)
- 書く派には、シンプルExcel家計簿もおすすめ
- 無理のない範囲でOK!
市販の手書きの家計簿を無理なく続けられる方は別ですが、可能であれば家計簿アプリをつかってみてはいかがでしょう。
いちいち手入力する必要はありませんし、日々の支払いをクレジットカードに集約すれば、どこで何を買ったのかが簡単に把握できるでしょう。
「家計簿をつけたくても入力するのが面倒くさい…」「レシートを整理するのは億劫」という方には、資産管理アプリがおすすめです。
ステップ3:「振り返る時間」を週1でも行う
支出を記録するだけでは、家計管理の改善にはなりません。きちんと内容を振り返る時間を設けてください。
家計管理が安定してくると支出する金額も固定化され、振り返る時間や回数も減っていきます。
振り返るコツとしては以下の通りです。
- 1週間の支出合計だけでも見るすると意識が変わる
- 「赤字」の週も気にしないで続けることが大事
1週間の支出合計だけでも確認する
短い期間でも支出の合計額を確認してみると、例えば「コンビニに2回も行ってしまった」「日用品を二重で購入してしまった」「これムダだったかも」と気づくことでしょう。
小さな気づきが見えて意識が変わっていきます。継続していくと、改善点も見えてくるでしょう。
「赤字」の週も気にしないで続けることが大事
赤字の家計が続くとやる気が無くなったり家計への不安があったりするなど考えられますが、あくまでも続けることが大切です。見える化によって意識が変わり、不安も軽減されるはずです。
我が家の「見える化」実例
我が家が行った見える化は「家計簿アプリ」を利用して徐々に支出の見える化を図っていきました。今では月に1度は夫の家計管理会議を行っています。
実際に我が家で行っている家計の見える化について紹介いたします。
- 家計簿アプリの利用
- 固定費と変動費の見える化ができた
- 夫とのお金の会話がしやすくなった
家計簿アプリの利用
我が家では家計管理アプリ「マネーフォワードME」を使っています正確に言うと、「住信SBIネット銀行」と連携している特別版を使っているのですが、基本機能はほぼ同じなので、今回は「マネーフォワードME」として紹介します。
公式サイトURL:https://moneyforward.com/
マネーフォワードMEは、さまざまな資産の記録を自動で取得してくれる大定番の資産管理アプリです。
アプリと口座、クレジットカードを紐付けることで自動的に収支を仕分けしてくれるため、紙で家計簿をつけるのと比較して記入の手間や漏れがなく、楽に管理できる点が特徴です。
銀行口座やクレジットカードはもちろん、株式やFX、電子マネー、仮想通貨など幅広い資産の情報を自動で取得してくれます。
自分が何にどのくらい使っているのか、預貯金と株式のバランスを一目で把握することも可能です。
支出は項目ごとに分類してグラフ化できるため、何にいくら使ったのかが一目で把握できる点もメリットです。
資産管理はもちろん、支出データもわかりやすく把握したいという方におすすめのアプリです。
アプリについてですが、有料版の方が機能が充実していることが多いです。ただし、資産運用に積極的でない方や口座連携させる数が少ない方は無料版でも問題なく使用できるでしょう。しかし、収支の過去データが1年間分だけしか見れないなどのデメリットもあるので、始めは無料版で試してみて、やっぱり有料版がいいと思えば、切り替えていくものよいでしょう。
最初から有料アプリに課金するのではなく、無料アプリで使用感を確かめてみましょう。
ここで注意しておきたいことが1点あります。
投資関係は最初は紐付けしない方がよいということです。投資部分については、例えば新NISAに毎月〇〇円投資していると言うように、お金の流れがざっくり分かる程度で十分です。万が一、証券口座と紐付けすると投資利益の増減が気になりすぎて、マネーフォワードのアプリばかり毎日見てしまう可能性があります。

家計管理に慣れてきて、どうしても証券口座と連携したい場合は行ってもよいかもしれません。マネーフォードは日々の収支の見える化がすごくスムーズになって、もう手放せません。
固定費と変動費の見える化ができた
最初は不透明だった固定費と変動費ですが、支出の見える化を行うことにより改善点が分かっていきました。
固定費の削減や変動費の毎月積立を行うなどして、今では家計に余裕が出てきました。
「ストレスをためずにできる家計管理の3ステップ」を別の記事で紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
夫とのお金の会話がしやすくなった
私の夫はもともと浪費家タイプではありませんので、お金の話に対してそこまでハードルは高くはありませんでした。
しかし、マネーフォワードに私と夫の群行口座やクレジットカードを全て紐付けすることに関しては多少の課題がありました。
まず、家計簿アプリに自分の銀行口座やクレジットカードを連携させることが怖かったようです。当たり前ですが「知らない」が一番の不安でしょう。
しばらくは私だけ銀行口座を紐付けして様子を見ることにし、慣れてきたら夫に相談し、まずは試しにやってみようということになりました。

今では、毎月の締め日には夫と家計管理会議を行っています。会議といっても、マネーフォードのグラフや支出の一覧表をもとに、「今月は少し外食が多かった、日用品費が思った以上に少なかった」などの内容です。あまり細かくは言いませんが、「今月もありがとう」という言葉を伝えています。ちょっとしたことですが、夫婦での家計管理がしやすくなるでしょう。
私の家計簿の失敗談
家計簿に関する記事は世の中に溢れています。今でこそ、スムーズに家計管理を行えるようになりましたが、私は独身時代から何度も家計管理に挑戦しては、失敗の連続でしたでした。しかし、過去の失敗があって今があります。
・失敗①市販の手書き家計簿
最初はやる気満々でしっかり記入してきましたが、途中でレシートなどを紛失したり、毎回記入することを忘れてしまったり、結果的に収支の金額が合わず挫折しました。この挫折は幾度となくありました。
・失敗②袋分けのでの家計管理
毎月、固定費および別にやりくり費(変動費)を一定額ずつ封筒に入れて管理することもたレンジしてみましたが、そもそも固定費の見直し等を行っておらず、予算が足りなくなり、予備費の封筒のお金に手をつけてしまい、結果的に赤字になっていました。
・失敗③直接入力する家計簿アプリ
自動集計するアプリでなく、あくまでも金額を直接入力するアプリです。最初に収入を入力し、支出額を入力して残金が分かるタイプのアプリを試してみました。
事前にカテゴリーを設定して、使った金額をカテゴリー別に自分で入力していきます。グラフは見やすいのですが、そもそもクレジットカードなどで使った金額などは自動計算してくれる訳ではなく、支出だけの記録となってしまう内容でした。上記の手書きの家計簿と同様にレシートを紛失したり、入力が疎かになったりして、やはり使いすぎて赤字が続いてしまい挫折となりました。

数々の失敗や挫折があり、今の方法に落ち着きました。たくさんの失敗があって自分の家計管理の最適化を見出すことができたと思います。
まとめ

今回は家計管理の第一歩を踏み出そうということで、家計の見える化を紹介しました。
毎日の忙しい中で、一度にまとめて行うのはなかなか難しいので少しずつ行っていきましょう。
もう一度、家計管理の見える化に取り組んでいく過程のポイントをお伝えします。
- 完璧すぎを求めない
- やり方は「自分に合うか」が大切
- 毎月いくら使っていて、どこにお金が流れているか?
- 無理なく節約できるポイントはどこか?
家計管理の中で見える化ができると、今まで漠然としていた不安が軽減されていきます。
もちろん時間がかかる方もいるかもしれません。
大前提に完璧を求めるのでななく、まずは、ご自身の家計について「意識を向ける」ことが大切です。
家計管理に取り組んでいく中で楽しさに気づき始めたらバッチリです。
もし、将来の不安が少しでもあるなら、家計管理の一歩を踏み出してみましょう。
ご自身の家計管理で気になるポイントやこんな家計管理で見える化できたよ!というアイデアがあれば、ぜひ教えてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
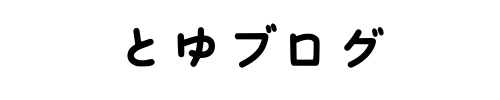
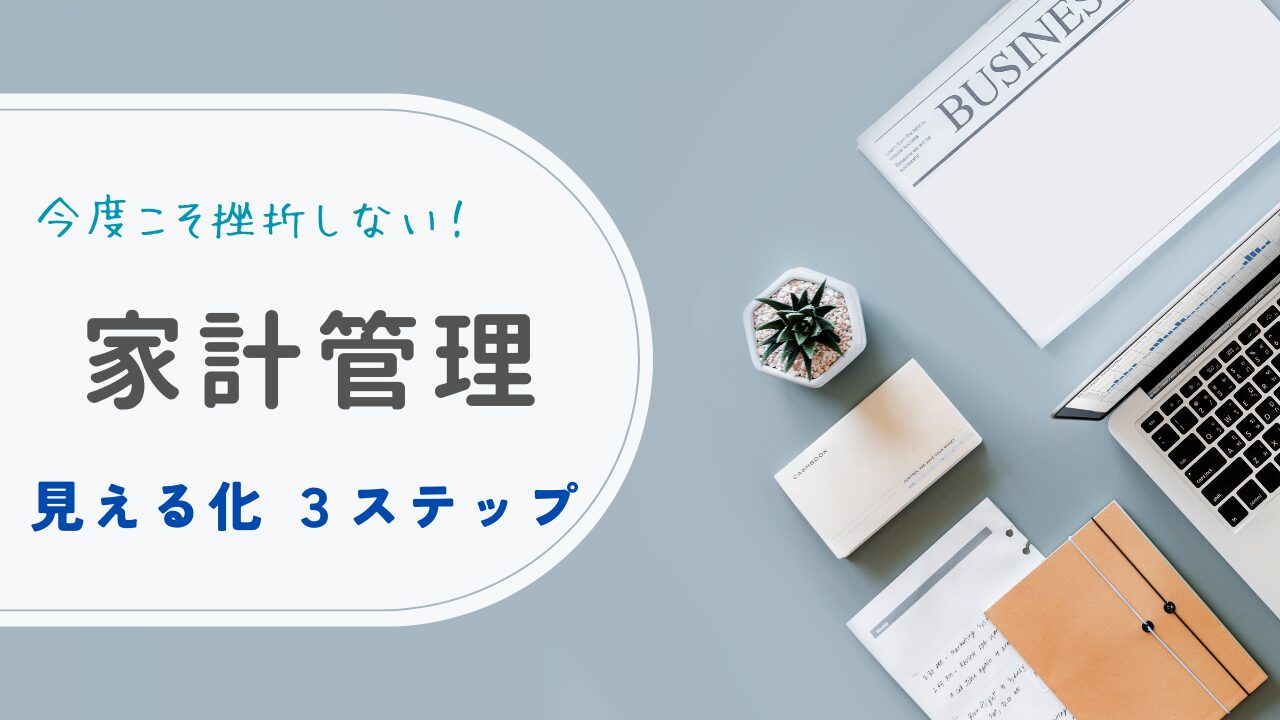

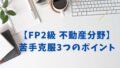
コメント