突然ですが、皆さんはいくら教育費があれば安心しますか?
「そんなの分からない」「いくらあっても足りない」など漠然と考えている方もいらっしゃると思います。
今回はFP2級保持者の私が現在進行形の体験ベースで行っている教育費の貯め方をお伝えします。子どもの教育費の貯め方で悩んでいる皆さんの参考になれば幸いです。
はじめに:教育費ってどれくらい必要?
進路別の教育費の目安(幼稚園から大学卒業まで)は以下のとおりです。
- すべて国公立:総額 約1,000万円
- すべて私立:総額 2,000万円以上になる場合がある。
1980年度の国立大学の年間授業料は約18万円でしたが、2005年度に約54万円に引き上げられ、その後2023年度まで据え置かれています。
2025年度からは東京大学など一部の国立大学で約64万円への引き上げも決定しています。私立大学の平均授業料も、1980年度の約38万円から2023年度には約96万円へと2.5倍以上に増加しています。理系学部の場合は授業料がさらに高く、初年度納入金(入学金・施設費等含む)は150万円を超えるケースが一般的です。
詳細は下記の参考資料をチェックしてみてください。
【参考】
旺文社教育情報センター「大学『学費』の推移を見る」(2025年3月13日発行) https://eic.obunsha.co.jp/file/educational_info/2025/0313_1.pdf
文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」
https://www.mext.go.jp/content/20211224-mxt_sigakujo-000019681_4.pdf
子ども一人当たりの教育費は進路によって大きく異なります。
すべて国公立に進んだ場合の総額は約1,000万円ですが、すべて私立に進むと2,000万円を超える場合もあります。幼稚園から大学までにかかる費用は、進学する学校の種類(国公立か私立か)や、大学の通学形態(自宅通学か自宅外通学か)によって大きく変動するため、家庭の教育方針に沿ってシミュレーションすることが大切です。
幼稚園は私立で大学も私立、その他は公立とした場合でも私立の大学は国公立大学の約4倍の入学者があることから、このケースの場合は、オール私立ほどではないにしても、多くの費用がかかります。大学や専門学校では授業料のほかに、教科書代や実習費などもかかります。
進学先が自宅通学か自宅外通学かでも大きく変わっていきます。
自宅外通学の場合、食費などが親の負担となるため、自宅通学の場合よりも費用が大きく増える傾向があります。
大学等の進学以前にも成長過程に関わる費用として学校外活動費があります。
これは、幼稚園や学校以外での習い事や塾などでかかる費用で、全体の費用を押し上げる大きな要因です。
例を挙げるほど教育費は膨大であり、不安も募りますよね。

私自身も晩婚で世間でいう高齢出産の部類で子ども1人授かりました。
一生独身でいるとずっと思っていたので、教育費は特に考えず・・・
しかし、現在は教育費・老後資金・この先の介護資金も必要となっている我が家です。数字上では家計管理を始める前はかなり焦っていました。
我が家の貯め方ステップ
我が家の教育費の貯め方ですが、子どもが産まれる前に考えていた内容です。
今、中学生や高校生のお子さんがいる家庭では当然当てはまらない部分もあると思います。
ここでは出産前〜小学生低学年くらいのお子さんをお持ちの方に向けての内容と思っていただければと思います。
以下3つのステップを導入しています。
- まず、目標金額を決める(ある程度目安でOK)
- 児童手当は死守
- 現金貯蓄だけではない方法も導入する
目標金額を決める
まず子どもを授かった際に貯める教育費の目標額は「500万円くらい」と考えていました。
この頃は、まだ家計管理もFPの勉強も行っていませんでした。
ネットで検索した際におおよその目安として考えたものです。
ただし、ある程度の見通しを立てておくのがよいと思います。
子どもが生まれて「この子がやりたいことをやらせてあげたい!」と思うのが親心かもしれません。
しかし、教育費は聖域になりがちです。あれもこれもと出費があった場合は、自分たちの老後資金等にも影響が出てしまいます。
私立も考えて教育費は1000万を目安とか家計的に厳しいから200万を目指してあとは奨学金に頼るとかの選択肢をお持ちの方もいると思います。
子どもが生まれて単純に大学等に進学するまで18年間あります。ある程度の期間がありますので、しっかり準備をしていきましょう。
目標の金額があれば、達成するまで「あと、いくら貯めるか」の過程も明確になり、貯めるためのモチベーションアップにもつながります。
先に述べたように我が家は晩婚家庭なので、教育費に対して危機意識が少し高いかもしれません。
児童手当は死守する
児童手当は、その時代によって金額や制度が変わる手当です。
現状は子どもが3歳になるまでは月額15,000円、3歳〜18歳までは10,000円まで支給されます。第3子になると金額も増額されます。
「子どもの教育費の貯め方」で検索すると、「児童手当を充てる」ということがよく見かけられます。
私自身もこの方法を取り入れています。ここで注意したいことは、「絶対に児童手当には手をつけない」ということを徹底することです。
子どものための児童手当なんだから、さすがに手をつけないでしょう?と思うかもしれません。
しかし、日々の生活に追われているのに収入が上がらない、家計が厳しいとあれば使ってしまう可能性もあります。

私自身はもとはかなりの浪費家だったので手をつけてしまう怖さがありました。
そこで、子どもが生まれたあとすぐに、子どもの名義で紙の通帳があるゆうちょ銀行を開設しました。その際はキャッシュカードは作らず、子どもの口座に愛着が持てるように子どもの誕生日・生まれた時に計測した身長・体重の数字と同じ金額を入金し、「この口座は大事なもの」とさらに認識させました。
児童手当の受給者は自分なので、dNEO BANK(旧:住信SBIネット銀行)で入金された児童手当はすぐにスマホで子どもの口座へ送金しています。
加えて毎月1万円ずつ自分の口座から自動送金しています。
わざわざ紙の通帳にこだわる必要はないかもしれませんが、私はあえて出金する手間を作っています。金融機関に行って出金用紙に金額を書いて、子ども名義の印鑑を押印する手間は考えただけで面倒です。安易に引き出さない仕組みづくりも大切です。
制度改正もあるかもしれませんが、単純に子どもが高校を卒業するまでに全て貯めれば約200万円ほどになります。かなり大きな金額になるので、中長期で教育費を貯めるなら絶対にオススメです。
現金貯蓄だけに頼らない方法も導入する
教育費はある程度長い年月をかけて準備するものです。明日から大学に入学するからいきなり300万を用意するなんてことはありません。
家族構成や年齢、子どもの人数によって選択肢は変わってくると思います。大切なのは家計の状況をきちんと把握することです。無駄な固定費の削減や変動費の積み立てなど少しずつでもいいので見直しを図りましょう。
現金だけでなく違った方法も組み合わせて準備することも大切です。代表的なもので「学資保険」「つみたてNISA」などあらゆる方法が世の中にあります。
子どもを授かった際に私自身もネット検索をかなり行い、当初は学資保険を選択肢に入れていました。しかし、思っていた以上に満期になった際の返戻金が少なく、自分が亡くなった場合や働けなくなった場合の免除制度は充実していましたが、生命保険でカバーできる内容だったので加入することはしませんでした。当時は掛け金が高めの貯蓄型保険にたくさん加入していたので、学資保険は不要であると判断することになりました。

まだFPの知識どころか投資の知識も全くない状況でした。投資は怖いイメージがあり、今更ながらもっと早く始めていたらと思っています。
我が家はジュニアNISAの最後の年に駆け込み申し込みを行い、80万円を一括入金しました。そこからはずっと放ったらかしです。
証券口座の管理画面は年に1〜2回しか見ないのですが、先日確認したところ約プラス38万円でした。もちろん投資なので暴落もあり得ますが、普通に銀行口座に入金しただけでここまでは増えることはありません。
ジュニアNISA制度はすでに終了しているので、今後は特定口座で取り引きを行っていくか、老後資金のために現在行っている新NISAの金額を増やして教育費に活用していくかは模索中ですが、今のところは現金貯金とジュニアNISAだけのシンプルな方法で進めていこうと考えています。
教育費を貯めるためのポイント2つ
我が家の教育費の貯め方の現状をお伝えしましたが、晩婚+一人っ子だからできる方法ではと考える方もいらっしゃると思います。確かにそう思われるかもしれません。ただし、児童手当の将来の教育費の死守や現金貯金のやり方は家庭状況が異なっていても必須だと考えます。
上記を踏まえて、教育費を貯めるための2つのポイントを紹介します。
- 目的別に分けて貯蓄する
- 固定費の見直しを行う
目的別に分けて貯蓄する
教育費を貯蓄するには目的別に分けて貯蓄するのがオススメです。
例えば、学校の教材費など日々の教育費については毎月の家計から変動費として貯蓄しておくとよいでしょう。変動費といってもあらかじめ予算は立てやすいと考えます。
おおよそ2〜3千円くらいでしょう。学年があがり塾や習い事などになった場合はサブスク費として個別に支出を分けておきましょう。
短期的な教育費と中長期的な教育費と一緒にせずつに積み立てておくとライフプランが立てやすくなります。
固定費の見直しを行う
日々の生活には何かとお金がかかります。教育費だけ貯金すれば良いとは言えません。他にもさまざまな場面で必要な経費が家計を圧迫します。そのためには、固定費の見直しを行うとよいでしょう。どこかに無駄な支出があるのではないか?毎月の生命保険料や通信費などを見直してできるのではないか?と気がつく項目があると思います。
固定費は一度見直すとその効果がずっと続きますし、削減できる金額も大きいと思います。
貯蓄や投資にまわせる金額が増えれば気持ちにもゆとりが出てきます。
固定費の見直しについて下記の記事を参考にしてみてください。
まとめ
今回は、子どもの教育費をいくら貯めるかというテーマで我が家で実践している内容を紹介しました。我が家のやり方が全て正解ということはありません。しかし、元浪費家の私がFP2級の勉強で身についた知識と家族の協力でシンプルかつ堅実な方法で教育費を貯めています。
最終的にいくら必要かは、子どもの進路によって大きく変わります。なるべく早い段階から将来の教育方針について話し合い、家族でシミュレーションを行うことが重要です。
無理のない範囲で今できることを少しずつ実行していきましょう。
本音を言えばもう少し現金貯蓄や投資にまわせる金額を我が家も増やしていきたいと考えますが、度を超えた節約など無理も禁物かと思います。
今を楽しむ気持ちを少し持ちつつ、将来子どもが困らない親心も大切にして、無理のない貯め方で将来に備えていきたいと思います。
皆さんの教育費の貯め方でオススメな方法や工夫があれば、ぜひ教えてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
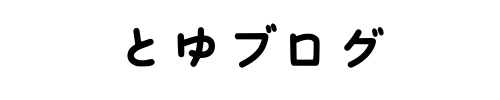
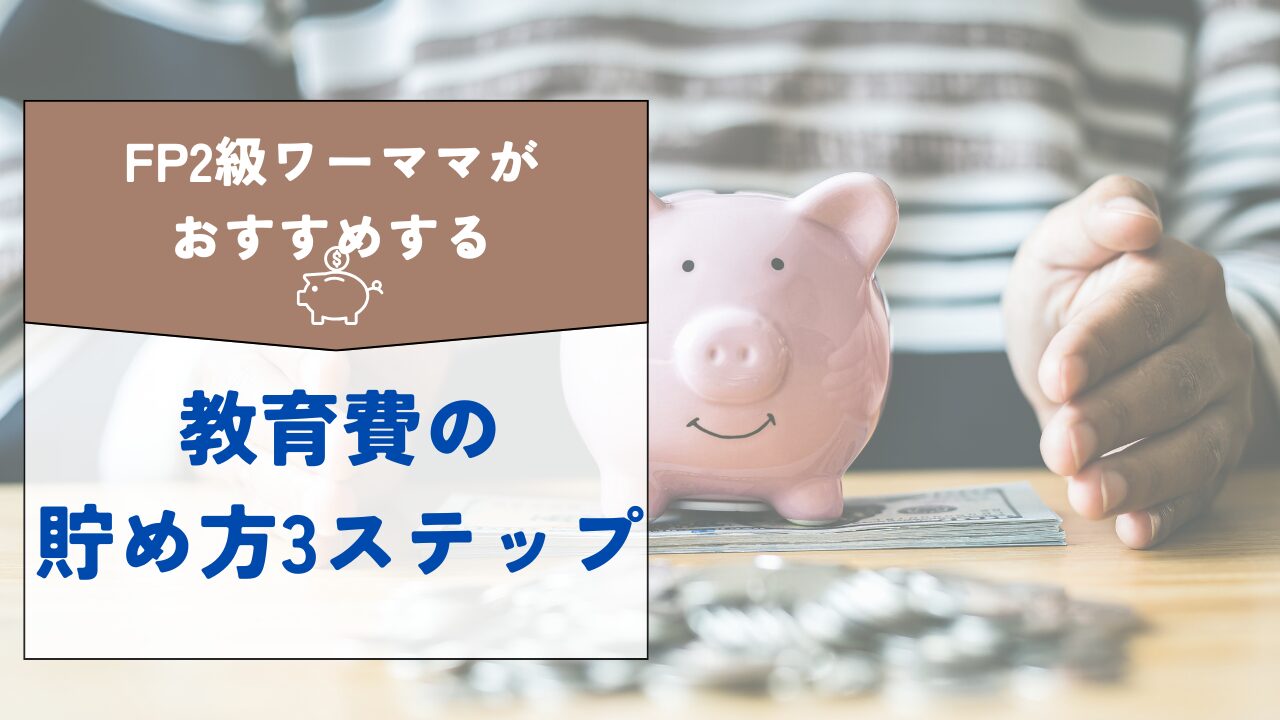




コメント